
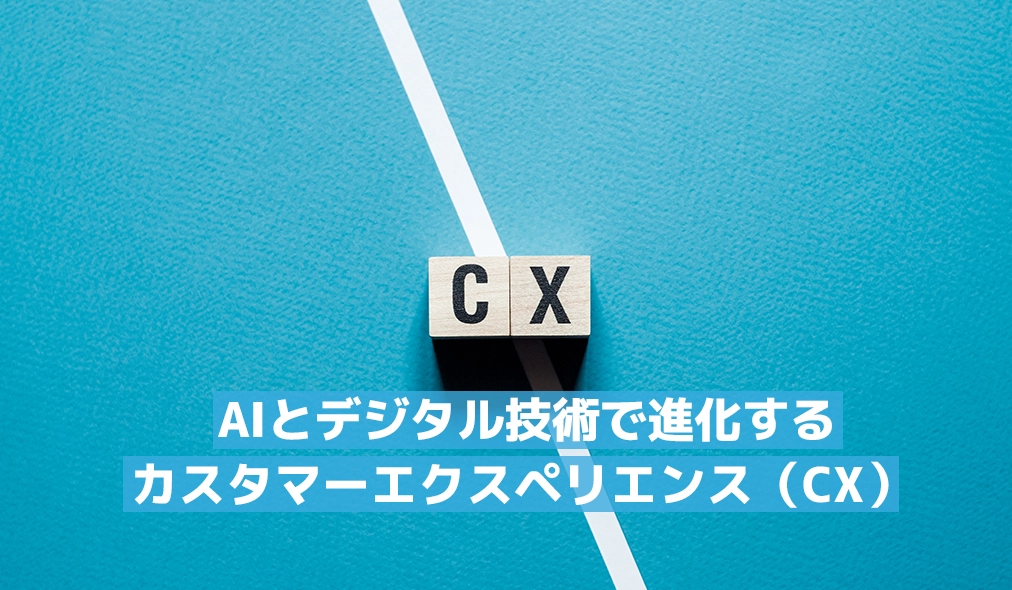
![]() 2025.07.24
2025.07.24
![]() 2025.07.24
2025.07.24

顧客が商品やサービスを選ぶ時代、企業は「顧客体験」を創造することが欠かせなくなっています。CX(カスタマー・エクスペリエンス)向上の重要性や顧客ロイヤルティの高め方に関心を持つマーケターの方も多いと思います。しかし、CXマネジメントの定義やCRM、カスタマーサクセスとの違い、導入のメリットやツールの選択方法については、まだ十分に理解が進んでいないかもしれません。
本コラムでは、顧客体験マネジメント(CXM)の最新概念、企業成功事例、具体的なマネジメント手法や施策の導入プロセスを調査・分析しながら解説します。多様な接点を持つ企業のCX創造の方針やデータ活用、AIやSaaSツールの価値、業界ごとの戦略比較まで、実践的な情報を掲載。CXM導入を考える方の疑問を解消し、自社事業の成長を支援します。
目次
顧客体験マネジメント(CXM)は、企業と顧客がやり取りする全ての接点や経験を包括的にマネジメントし、両者の間により大きな価値を創造するための最新のマーケティング概念です。近年、CX(カスタマーエクスペリエンス)およびNPS(ネットプロモータースコア)の活用を含めたCX向上の重要性が増しています。例えば、コーヒーショップで商品を購入する顧客は単に「コーヒーそのもの」や「味」だけでなく、休憩時間の安らぎやスタッフとのコミュニケーション、同僚との談笑、さらにはフェアトレードコーヒーによる社会貢献など多角的な体験に価値を見出しています。
CS(カスタマーサティスファクション)が「満足」の提供、CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)が「関係」の管理だとすれば、CXMは商品・サービス購入から利用、アフターサポートまで「顧客体験」の質を戦略的にコントロールし、顧客ロイヤルティや企業収益性の双方を追求します。
CXMの最新ツールや分析データを活用しながら、顧客体験を深く理解し、NPSやお客様の声(VoC)などの調査により優先課題や改善点を見つけ出し、各接点で価値創造を続けていくマネジメント手法が求められています。
このように、顧客が自社の商品やサービスを選び続けてもらうためには、単なる「商品・サービス価値」だけでなく、「体験価値」を最大化し、LTV(顧客生涯価値)の向上に取り組むことが不可欠です。CXMを経営方針や事業戦略として導入することで、顧客満足だけでなく企業としての持続的成長にもつながります。
CXMは、企業が顧客とのすべての接点を通じて提供する体験全体を管理するアプローチです。CRM(Customer Relationship Management)は長年運用されているマーケティング用語で、顧客との関係構築を情報システムやデータベースを活用して管理する手法にフォーカスしています。CRMは特に、顧客ニーズへの対応や自社の差別化、長期的関係の維持拡大が主目的です。
一方、CX(カスタマーエクスペリエンス)は“体験そのもの”に重きを置き、CS(カスタマーサティスファクション)は“満足”の度合いに注目します。CXMは商品やサービス購入だけでなく、その前後の体験まで設計し、価値ある経験を追加することで顧客ロイヤルティの向上やLTVの最大化を目指します。
また、CXMの特徴は、顧客が体験する“感情”や“印象”に寄り添うことで、単なる数値以上のブランド価値を創出する点です。近年のマーケティング戦略では、CRMやCSで蓄積してきたデータと、CXMがもたらす体験の質を融合させてシナジーを発揮する事例も増えています。
こうした違いを理解したうえで、顧客・企業関係の進化や各マネジメント手法の役割を整理すると、CX向上や顧客ロイヤルティの獲得を実現するには、CXMの導入と定着が不可欠と言えます。
CXMを導入する企業が増えている背景には、顧客ロイヤルティの向上とLTV(顧客生涯価値)の最大化が期待できる点があります。CXMを戦略的に活用することで、自社商品やサービスのファンとなるロイヤルカスタマーが増え、安定的な売上が見込めます。
さらに、ロイヤルカスタマーによるポジティブな口コミやSNSでの推薦が強力な集客につながる事例も増加しています。現代では、顧客の“声”がマーケティング効果を大きく左右する時代となっており、体験価値の差別化が企業競争力の重要要素となっています。
また、CXMの実践により、競合他社との差別化が明確になり、価格での安売り競争から脱却できる点もメリットです。多様な消費者ニーズや商品比較が常態化したいま、CXマネジメントが顧客選択の理由となることは大変価値が高いです。最終的に、顧客接点を高度に設計し運用できる企業が、マーケットで選ばれるようになります。
CXMの重要性が国内外で高まるなか、成功させるために意識すべきマネジメント戦略は複数あります。まず、明確なゴール設定によって体験価値向上の方向性を決めることが大前提です。また、顧客それぞれの違いやニーズを丁寧に把握したうえで、多様な取り組みを展開する必要があります。
顧客体験の中で本質的に改善すべき優先課題を調査やVoC(顧客の声)などのデータ分析により見極め、経営方針や部署ごとの方策に具体的に組み込んでいくことが重要です。
加えて、現場で継続的に運用できる実践的な設計をすることで、理論倒れにならず日々のCX業務につなげることが可能になります。世界的にもCXMは企業価値創造の中核を成す概念となっており、日本企業がグローバル競争を勝ち抜くためにも、CX戦略の徹底が求められています。
カスタマー・エクスペリエンス・マネジメント(CXM)は、顧客満足のその先を目指し、接点全体で最適な顧客体験を提供する取り組みです。CXM導入の第一歩としては、自社顧客の体験を網羅的に可視化し、どこに価値や課題があるのかを分析することがポイントとなります。
こうした分析では、NPSやVoC調査、各種分析ツールを活用する手法が効果的です。続いて部門横断で共通認識を持ち、商品やサービス設計、カスタマーサポート体制、マーケティング施策など、多層的な方針決定をする必要があります。また、自社に最適なカスタマーサクセスツールの比較・選定もカギとなります。サービスの特徴や導入目的、運用コストや機能などを比較し、事業とCX戦略にベストなシステムを活用してください。
Webコンテンツ、ECサイト、実店舗など様々なチャネルを連携させ、データを蓄積・分析しながら、パーソナライズされたCXの実現を目指すことが現代経営のスタンダードとなっています。結果として、組織全体の取り組みでCX向上を実現し、高いLTVと持続的な成長につなげる流れが生まれます。
顧客との接点を強化することはCX向上の土台となります。体験価値を高めるためには、単に「商品」を売るだけでなく、それに付随する体験全体を設計するマーケティング・コミュニケーションが必要です。
例えば、カフェではコーヒーの味以外に、居心地のよさやスタッフとの会話、環境への配慮といった点も顧客体験の一部となります。こうした体験価値を最大化するには、店頭やWebサイト、カスタマーサポートなど多様な接点で一貫したコミュニケーションを意識することが大切です。
NPSやCXツールで顧客の声を継続的に拾い、感情データに基づいた改善施策を積み重ねることで、顧客ロイヤルティ向上やLTVの増大が期待できます。
顧客から得られるNPS、VoC、口コミなどの「声」をデータとして収集・分析し、そこから新たな価値を創造することがCXMの中核となります。まずNPSで顧客ロイヤルティを測定し、VoCで具体的な不満や要望を把握できます。
こうしたデータをカスタマーサクセスツールやCRMシステムで一元管理し、セグメントごとに課題や傾向を分析します。AIや最新の分析機能を利用することで、見えにくい改善ポイントや隠れたニーズも可視化できます。
分析結果をもとにCX戦略や商品・サービスの改善、プロモーションへと反映させることで、顧客満足度や事業成果の向上といった価値創造へつなげることが可能です。
CXM導入で成果を上げる企業は、自社の顧客体験を正しく分析し、SaaSツールを駆使した運用で、顧客ロイヤルティやLTV向上を実現しています。CXMツールを導入すると、各顧客接点や体験の質を定量的・定性的に把握しやすくなります。
その結果、ファン顧客の育成や、彼らによるポジティブな口コミ拡散がブランド価値の向上を促進する事例も多くなっています。競合他社との差別化や、単純な価格競争ではなく体験価値勝負へとシフトできるのも大きな強みです。
また、現場スタッフの業務改善を伴うCXマネジメントが定着しやすく、組織全体で顧客志向の文化を育みつつ持続的なビジネス成長へとつながっています。
カスタマーサクセスツールやCRMシステム選びでは、顧客体験マネジメント(CXM)の目的や自社の課題に適した機能比較が重要です。CSやCRMは時代とともに進化してきましたが、現在は顧客との多様な接点から得られるデータを分析し、体験価値向上に活用できるCXマネジメント機能が求められます。
選定のポイントは以下の通りです。
上記の機能を比較し、導入目的と現場の運用負荷を踏まえて選ぶ必要があります。CXMツールとの連携性も見極め、カスタマーサクセスやCX向上の最適解を目指してください。

CXMは、企業と顧客の関係や満足度の変遷を踏まえ進化してきたマネジメント概念です。成長が鈍化した成熟市場では、既存顧客のロイヤルティを高め、長く支持されるブランドへの発展が重要性を増しています。また、モバイルやインターネット技術の発展により、顧客接点が増加・複雑化したことで、体験全体の包括的な管理が不可欠となりました。
CXMの運用では、顧客からの声や感情、購買単価や反応をデータとしてつなげ、高度に活用します。データ分析だけでなく、実際の体験設計や現場マネジメントまで含めて一体となった運用を進めることで、単なる満足度向上ではなく“ファン化”を実現可能です。
CS(カスタマーサポート)の丁寧な対応、CRMの関係管理にCXMで得た体験情報を掛け合わせることで、より深い顧客理解とサービス向上が進みます。
このような一連のプロセスを通じて、企業はCX戦略やVoC分析を軸とした差別化施策により継続的な事業価値創造と競争優位を確立することができます。
市場環境や顧客ニーズの多様化を背景に、CXMは様々な客層やセグメントに合わせた施策展開が求められます。会員向けならパーソナライズ案内やロイヤルティプログラム、ECサイトならAIレコメンドやリアルタイムチャットサポート、店舗なら店舗体験やスタッフによる接客サービスなどが挙げられます。
こうした施策を成功させるためには、顧客の声(VoC)や購買データを細かく分析し、顧客セグメントや接点別施策を最適化することがポイントです。既存顧客が長くブランドを選び続ける仕組みを創ることで、時代の要請に応えるCXMの価値を最大化できます。
特にデジタルとリアルを融合したCX創造やファン化を狙う戦略が、有効な差別化手法となっています。
AIやMA(マーケティングオートメーション)ツールの導入は、CXM実現における自動化・パーソナライズ戦略の要です。AI分析によって顧客ごとの属性や嗜好を抽出し、MAでタイミングや内容を最適化したコミュニケーションを自動配信できます。CXMツールやサクセスソリューションでは、NPSや顧客声の収集、行動データの蓄積・分析も簡単になり、個々の顧客ニーズや価値観に応じたアクションが可能です。
このようなAI・MAの活用は、Web、CRM、ECなど多様なチャネルの連携も促進し、効率性とCX最大化を同時に実現できる戦略と言えます。
CXMの成果測定には、的確なKPI設定と継続的な分析・テストが不可欠です。最初に自社の優先顧客や重要接点を洗い出し、その実態データから改善可能なKPIを設定します。
適切なKPI例のポイントは以下の通りです。
などが挙げられます。
これらのKPIを定点観測し、CXツールや分析システムでPDCAを回すことで、アプローチの適正や施策の有効性を検証できます。分析結果をもとに定期的なA/Bテストや改善策の実装を継続する姿勢が、CX向上実現の近道です。
CXMに取り組む際に企業が抱える課題や失敗例には、ゴール設定の曖昧さや全社展開の難しさ、顧客ごとの差異を無視した一律施策、現場の運用設計不足などが挙げられます。
成功のポイントは以下の通りです。
現場スタッフや経営層が一体感を持ち、CXへの投資とデータ活用を積極的に進めることも求められます。近年では、CXMツールが増え、支援実績豊富なツールの活用も有効で、カスタマーサクセスと接点管理・分析力を高めることで、CXマネジメントの実現性が大きく高まります。
顧客体験マネジメント(CXM)は、顧客が企業と関わる全ての接点で価値のある体験を提供し、長期的なロイヤルティやファン化を実現する戦略的なマネジメント手法です。商品やサービスそのものだけでなく、その背後にある感情や価値観、さらにはスタッフとのコミュニケーションやブランドへの共感までをデータやツールで可視化し、継続的に最適化していくことが求められます。
コーヒーショップの事例に見られるように、顧客が求めるのは単なる商品としての「効能・品質」だけではなく、日常の安らぎやスタッフとの温かなやり取り、社会貢献の実感など多角的な体験です。こうした体験全体を把握し、CX・NPSなどで“顧客の声”に耳を傾け、事実ベースで業務改善をすることがCXMの基本方針となります。
今後、自社のマーケティング戦略でCXMを活用するためには、まず現状の顧客体験を分析し、優先課題を明確にして段階的な改善を推進する必要があります。CXMツールを活用してプロフェッショナルな支援サービスやデータ分析ツールの採用も、CX構築の強力なサポートとなります。
これから本格的にCXMへ取り組みたい企業は、CXMツールの導入や内製化を視野に入れ情報収集を始めてみてください。