

建設業でWebを活用した集客に成功すると、市場競合が激しい中で自社の強みをアピールしやすくなります。そこでFacebook広告やDSP広告などピンポイントでアプローチできる広告やSNS対策を導入する業者が増えているのも理由の一つです。
本コラムでは建設業界向けのホームページ制作やSEO、DSP広告、リスティング広告などの具体的施策を解説し、営業成約に直結する改善ポイントを整理します。
Webを活用したマーケティングで他社との差を生み、利益に繋がる手法を解説し、MAツールやオンライン施工管理システムのメリットを知れば、会社全体の効率向上が期待できます。顧客のニーズを分析し、自社のサービスを最適にアピールする戦略を立てることで、競合企業よりリードを広げましょう。
目次
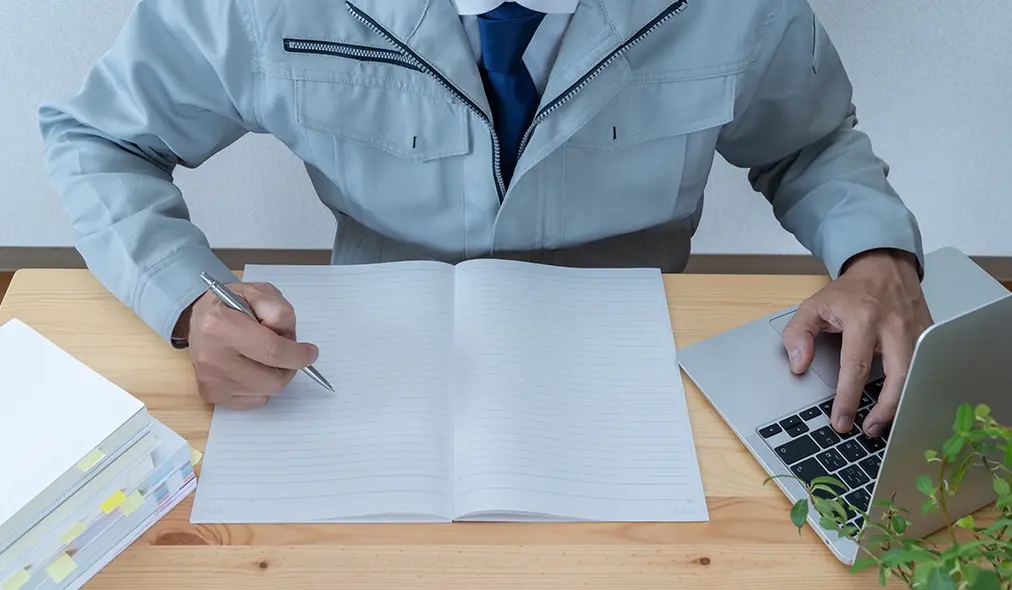
従来の建設業では、元請けや下請けのつながりを頼りに仕事を請け負う流れが一般的でした。Webの活用が進む今、ホームページやWeb広告、SNSを使って自社の強みを効果的に打ち出し、新規のお客様を獲得することが重要になってきています。Web広告の出稿やSEO対策など、競合が増える中でもピンポイントでターゲットに届く広告配信手法を方法を知ることが大切です。建設業でWebマーケティングを取り入れるときは、営業の流れを以下のステップに重ねて考えるとわかりやすくなります。
このように、自社サイトで実績や特徴を示して企業や人へオンライン上で接触し、見込み顧客を営業につなげる方法は、下請け構造に左右されない利益拡大にも繋がりやすくなります。建設業特有の課題を抱えながらも、新規案件を開拓するうえでWeb広告、Webマーケティングの運用は欠かせません。情報が集まるインターネットで販路を開拓するメリットは大きく、必要に応じて広告代理店の支援を受けるとさらなる成果も見込めます。さらに、他社との差別化を図ることで、市場でのポジショニングを高めやすくなり、こうした施策を進めるには目的を明確にしながら運用を継続することが望ましいです。建設業でのWebの活用は、これからも営業活動の柱になる。まずは4ステップを意識し、自社の施策を段階的に進めてみましょう。
顧客のニーズはインターネットを通じて素早く変化しています。建設業でも元請けや下請け関係に依存したアナログな集客や営業だけでは、広範囲なターゲットを取りこぼしかねません。2022年頃から続く社会のDX化とデジタルシフトにより、ホームページやSNSを活用したマーケティングが集客に直結しやすくなっています。施工実績やサービスの特徴をオンラインで発信すると、新規のお客様だけでなく企業からの問い合わせも増えるケースがあります
実力があるのにも関わらず集客が伸び悩む業者は多く、Webで情報を発信しないと、競合企業と比べて検索結果で表示されず、会社を見つけてもらう機会を失いかねません。建設業界でインターネット集客が狙い目とされる理由は、施工実績を視覚的に示しやすく、他社との差別化が図りやすいからです。
下請けではなく元請けとして仕事を獲得するには、自社のサービスを工夫して発信する施策がポイントになります。また、広告だけでなく、中長期的には、SEO対策やSNS運用など多彩な方法があり、自社の強みを客観的に分析し、顧客や市場動向に合った手段を選ぶことが成果につながります。建設業でWebマーケティングを導入するメリットは大きく、市場はさらにオンライン化を加速させていく傾向にあります。Webを活用して企業価値を高める行動が、安定的な成約につながっていきます。
競合他社との差を生むには、自社が得意とする業務や施工分野を明確に示し、市場の中で存在感を高めていくことが効果的です。中・小規模の建設業者でも、Webマーケティングを使うと新しい顧客層にアプローチしやすく、ホームページやSNSなど、運用する媒体を選ぶ際は自社の強みやサービス内容を考慮する必要があります。
全てを自社でまかなうと負担が大きく、Facebook広告やWeb広告運用、SEO対策など専門性が高い部分では広告代理店など外部支援も視野に入れましょう。ポジショニングを確立するためには、他社がやっていない取り組みを積極的に打ち出し、SNSやブログで定期的に情報発信を行うことが重要です。結果として、限定的だった集客経路を拡大し、工事の受注や企業への認知度向上に役立てられます。

建設業界でのマーケティングは、競合や業者が少ないうちに始めると有利に働きやすく、Web広告の出稿やSNS運用、SEO対策といった施策を組み合わせれば、ターゲットに合わせた効果的な集客ができます。ただし、実践する前に目的を明確にしておく必要があります。売上拡大、サービス認知度向上、ブランディングや企業イメージ強化など、何を目指すのかを整理すると成果につながりやすくなります。
具体例として、ホームページに施工事例や口コミを掲載し、新規のお客様が増え、お客様から信頼を集めた業者の事例があります。そこでは、リスティング広告やDSP広告を配信しながら自社サイトのアクセス解析を駆使し、検索キーワードを調整して集客を伸ばしました。Webマーケティングの効果は継続運用によって高まり、改善を重ねることがポイントです。他社の成功事例を参考にしながら、競合企業との差別化をはかりつつ運用の効率を上げると、自社のサービスにマッチした顧客が集まりやすくなります。最終的には、目的と行動計画が明確であればあるほど、商談や成約数の増加に結びつきやすくなります。
自然検索で上位表示を目指すSEO対策は、広告費用を抑えながら見込み顧客を取り込める手段として注目されています。中・小規模の建設業者なら、競合他社が少ない地域やニッチなキーワードで上位を狙う作戦が有効です。適切な検索対策を行うには、自社のホームページを定期的に分析し、改善点を洗い出す必要があります。
営業担当者を中心に、顧客の悩みや注文時期を踏まえた情報発信を行うと優位に立ちやすく、自社で全てを行うのが難しい場合は、SEOの専門家に下請けを依頼し、マーケティング効果を高める方法も選択肢に入ります。ただし、SEOのデメリットは、3ヶ月~1年位と成果が出るまで時間がかかります。実際に成功事例を生んだ企業は、小さな自社サイトのブログ記事から始め、継続的な運用で成約につなげました。こうした取り組みは長期的視点で利益をもたらします。
リスティング広告は、検索結果に直接表示できるため即効性が見込める施策です。ただし、適切なキーワードを設定し、入札金額と広告文の管理を行わなければ費用対効果が下がる恐れもあります。ホームページへ流入したユーザーが問い合わせや商談に進むよう、広告の着地点を整備しておくことが大切になります。
中・小規模の建設業者が広告運用を成功させるには、以下のポイントを意識しましょう。
専門知識が必要な部分は外部の支援業者を活用すると効果的です。最初に予算を設定し、運用データを分析しながら徐々に最適化していくプロセスが望ましいです。費用対効果を追求することで、ネット上での新規顧客や商談の獲得を高めやすくなります。
建設業界でSNS集客を成功させるには、ビジュアル訴求や日々の更新がポイントになります。元請けや下請けといった取引構造に限らず、直接ユーザーとつながりやすいのがSNSのメリットです。ただし、一度に多くのユーザーへ届く可能性がある反面、投稿内容や運用の方向性を誤ると信用を損なうリスクも存在します。
インターネットによるビジネスチャンスが広がる中、従来の営業スタイルに加えてSNSを導入すると、新規のお客様や同業他社への企業認知度が上がりやすくなります。また、SNSを活用することで、新規顧客の開拓だけでなく、見積依頼や商談につながるケースもあります。自社のサービス内容を積極的に発信し、施工や打ち合わせの様子を具体的に示すと信頼度が高まります。逆に、ターゲットを意識せずに何でも発信するとブランディングにブレが生じるデメリットがあります。運用中の注意点を踏まえながら、SNSでの発信と従来の営業を組み合わせる方法が効果的です。新規顧客を獲得する集客チャネルを増やすと競合にも差をつけやすくなります。
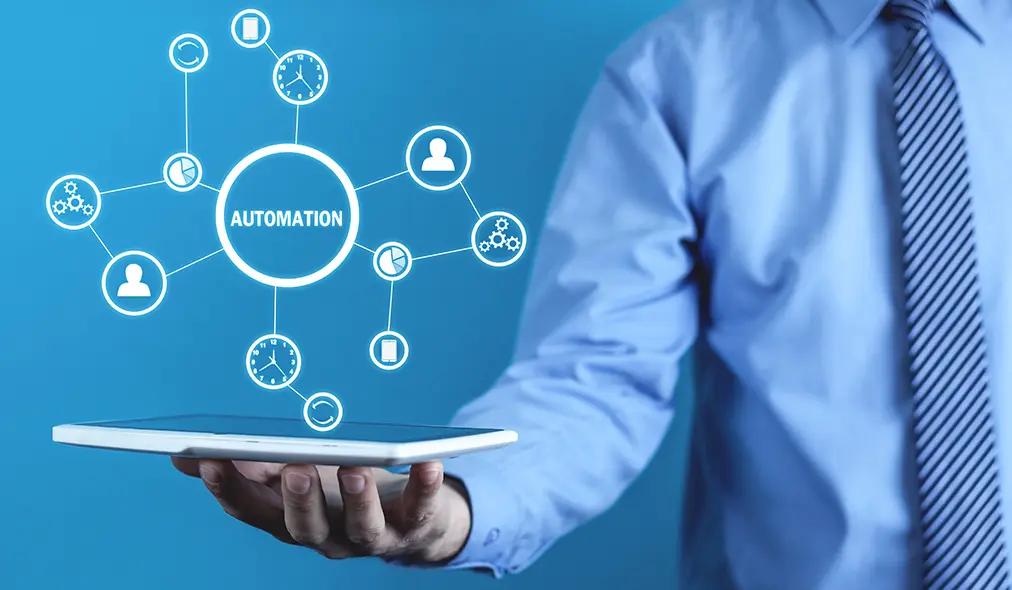
複雑化する建設業界の課題に対応するためには、自社のマーケティング活動を効率的に管理することが求められます。MAツールは、お客様のオンライン行動を可視化してフォローを最適化できるため、ターゲットを逃さず成約につなげる役割を果たします。ホームページやSNS、Web広告、DSP広告など複数の施策と連携させ、興味をもった顧客に段階的なアプローチを実施すると効果が高まります。
資材の価格高騰や人材不足など、建設業界は厳しい局面が多く、それでも需要は社会に欠かせない分野であり、安定した顧客獲得を実現するにはMAツールの導入で運用を管理し、効率を上げることが有益です。企業ごとの強みをアピールしやすくし、市場内でのポジショニングを明確にしておくと、オンライン上で新規やリピーターを取り込みやすくなります。自社の集客を着実に増やすためには、日々の分析と改善を根気よく続ける必要があります。
MAツールを建設業で活用すると、営業担当が行う顧客へのアプローチを一元管理しやすくなります。興味度合いや問い合わせ状況をシステム上で把握できるため、不要な連絡が減り、見込度の高い顧客へ集中できます。これによって営業効率が上がり、契約の見込み客を逃しにくくなります。
施策を実施する前には「自社のサービスをどう伝えるか」「顧客をどのページへ誘導するか」などを明確に決めると効果が高く、売上を増やす、知名度を上げるといった目標がはっきりしていれば、MAツールでステップを組み立てやすくなります。最終的に、見込み顧客の増加や成約率向上につながりやすく、会社全体の営業力を底上げできます。
多くの作業工程や関係者が絡む施工管理では、オンライン化による情報共有の効率化が大きなメリットになります。MAツールを取り入れると、問い合わせ段階から施工進捗、アフターサポートまで一元管理できるため、担当者同士の連携ミスが減ります。建設業特有の多重下請け構造でも情報が整理されやすく、現場とのやり取りが円滑に進みます。
それによりコストや工期の管理がスムーズになり、顧客満足度も上がりやすく、具体的な導入事例では、現場写真から契約書管理までシステム連携したことで、オフィスにいなくても施工状況を確認でき、瞬時に指示を出せるようになったケースがあります。視点を変えれば、新規受注だけでなく、既存顧客へのサービス品質を高める効果も期待できます。さまざまな工程をオンライン化することで、会社としての信頼度をさらに高められます。

建設業のホームページは、施工実績やサービス概要をわかりやすく伝える場となります。通常の営業と同様に、お客様のニーズを聞き取り実際に提案する流れを想定すると構成を組み立てやすく、Webマーケティングの方法は主に4ステップで、集客・接客・商談・成約へと進みますが、ホームページはこの最初の集客段階で大きく貢献します。
ターゲットや目的を明確に設定し、設計図のようにサイトマップをつくってから制作を進めると、余計なページを増やさずに済みます。施策として、シンプルなデザインと必要な情報の整理が重要です。Web広告やSEO対策と連動させ、問い合わせフォームや電話番号をわかりやすく表示すれば、商談につながる確率が高まります。建設業でホームページを作るときは、施工実例・費用・依頼手順など顧客が気にする点を丁寧に示すとWebでの集客を加速させやすくなります。
ユーザーが求めるのは、具体的な施工イメージや費用、実績の安心感です。中・小規模の建設業者でもホームページを使って有益な情報を提供すると、他社より上位に検索表示されるチャンスがあります。自社の強みとなる施工スタイルや品質、サポート内容をまとめ、「ここなら安心」と思わせるコンテンツを意識して作ると成果が出やすくなります。
こうした運用方法は、ホームページ制作後の継続的な更新にもつながります。制作して終わりにせず、分析ツールを用いながら改善を重ね、中長期的にサイトのクオリティを高めることが大事です。結果として、より多くの依頼や商談を獲得しやすい環境を作れます。
同業他社が増える中で、ホームページの分析と改善が集客に直結します。建設業界では、現場完工までの流れや安全対策などが注目されやすく、ビジネスのオンライン化が進む今、ホームページで情報を提示し、インターネット検索で発見される仕組みを構築すると他社との差が広がっていきます。
サイトのアクセス解析を行い、どの検索キーワードで来訪が多いか、市場ニーズはどこにあるかを把握すると見込み客への対応がしやすくなります。実際には、下請けや孫請け中心だった会社が、Webで元請け案件を獲得した事例もあります。改善施策としては、サイトデザインや導線を見直し、料金やサービスの特徴をわかりやすく提示しましょう。検討段階の顧客に適切な情報を与えると、商談へ発展するケースが増えやすくなり、こうした積み重ねが平均客単価の向上にも結びつきます。
継続的なWebマーケティングは手間と専門知識が必要になります。中・小規模の建設業者では、人手や時間が足りずに施策の準備や改善が滞ることがあります。こうした状況を避けるために、広告代理店の外部運用支援サービスの活用が効果的です。ホームページやSNSの更新、Facebook広告、DSP広告、リスティング広告の管理など、広告代理店のサポートを受けながら効率よく進めることで安定した成果を期待できます。
広告代理店など専門的な知識を持った運用支援サービスを利用すれば、広告の最適化や予算管理、SEO対策のポイントを掴みやすくなります。Webマーケティングの手段が多様化する中、プロのサポートで学びながら伴走し自社でも取り組む姿勢が重要となります。
建設業でWebマーケティングを進めるとき、自社だけで対策を完了させるのは難しい場合もあります。営業担当者や経営者が中心となり、必要な部分をプロに任せるスタイルにすると負担を抑えられます。自社で可能な領域は、顧客のヒアリングや施工事例の整理など、業務内容に精通した担当者がやるほうが魅力を伝えやすくなります。
外部支援を受けるときは、コストだけでなく実績やサポート内容を確認して選ぶことがポイントになってきます。どの媒体を使うのか、広告予算はどれくらいを想定するのか、具体的なサービス形態を事前に話し合っておけば、運用面でもスムーズに進みます。結果的にホームページやSNSの管理が行き届き、新規顧客の獲得に向けた道筋がはっきりしてきます。
Webマーケティングを活用すれば、下請けや孫請けに依存せずに自社の目的や特徴を大勢に伝えやすくなります。ターゲット層を定め、お客様の心理を想定しながらホームページやSNS、広告を組み合わせると成果が得やすく、特に競合他社が少ない分野や地域を狙う戦略は、より多くの商談や成約を目指すうえで有効です。
こうしたポイントを踏まえれば、建設業界でのWebマーケティングを成功へ導きやすくなります。次のアクションとして、まずは自社の強みや市場の状況を見直して、具体的なサイト運営や広告運用を始めてみましょう。広告費用や制作コストの捻出が心配な場合でも、段階的に進めながら改善を重ねることで十分な効果を得られる可能性が高く、Webマーケティングを取り入れることで、安定した集客と成約を実現します。
当社では、建設業界などBtoB向けのDSP広告を提供しています。部署・役職でのターゲティングや性別・年齢・興味関心などのデータ活用が可能な「Cpeers DSP」のお問い合わせは下記よりお気軽にお問い合わせください。